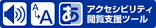品質を維持運用し
問題を未然に防ぐガイドライン
Webサイトの品質を維持運用するために遵守すべき
Webアクセシビリティガイドラインをお客様に代わって作成するサービスです。
メリット
- お客様のサイトに適したWebアクセシビリティガイドラインが得られます。
- お客様の制作ガイドラインにWebアクセシビリティの要素を埋め込むことも可能です。
サービスの説明
日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)の基となる国際標準規格のWCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) および WCAG 2.0解説書に記載されている情報は専門的かつ大量にあり、Web制作者でも、これをそのまま日常の制作ガイドラインとして用いることは容易ではありません。そこで、当社ではお客様のWebサイトに合わせた形で必要な事項を厳選し、お客様Webサイト専用に仕立てたガイドラインを作成しご提供しています。
新規にガイドラインを作成する他、現在ある制作ガイドラインの中にWebアクセシビリティの要素を埋め込むことも可能です。
Webアクセシビリティガイドラインの新規作成
ガイドラインを新規に作成する場合は、その使用の対象によって次の二つのタイプをご提供しています。
- Webサイト制作者向けガイドライン
日本産業規格(JIS X 8341-3:2016)が求める全項目について、1つの達成基準ごとに1~2ページ程度の事例入りで説明したガイドラインです。WCAG2.0の解説書を読まなくとも、おおむね内容が確認できるように全達成基準を網羅しています。
ページ数は、お客様サイトの実例をどの程度加えるかによりますが、50〜100ページほどになります。 - Web編集者向けガイドライン
CMSなどを用いてページ制作している場合は、編集者のできることには制限があります。その限られた範囲の中で、注意すべきことを整理したものがWeb編集者向けのガイドラインになります。通常は基本項目として10項目前後を選択し、それについて図解を含め易しく説明をしています。
ページ数は、手元において利用していただくことを第一に考え、25~50ページ程度のものになります。
その他関連サービス
Webアクセシビリティガイドラインに関連する次のサービスも提供しておりますので、ぜひご相談ください。
- チェックリスト作成サービス
制作会社様向けあるいは職員の皆様向けにシンプルなチェックリストを作成します。
ページ数は2ページから4ページ程度のシンプルなものです。
お客様のCMS環境などに合わせてカスタマイズしてご提供します。 - 既存ガイドラインのレビューおよび更新サービス
当社お勧めのサービスです。一般にWebの構築から運用までを行うには、制作ガイドライン、コーディングガイドライン、デザインガイド、運用ガイドラインなど、多くのガイドラインやガイドが同時に準備され運用されるのが一般的です。当社では、それらドキュメントがWebアクセシビリティの観点で不都合を起こしていないかを確認し、必要があれば内容を改善させていただいております。
FAQ
Q&Aの一覧